誰でも一度はベッドや布団で横になるものの「寝れない…」という経験はあると思います。
前回は不眠症の原因と種類について説明しました。
原因がわからない限り、いくら睡眠薬を内服しても改善しません。


✔︎ なかなか寝つけない人
✔︎ 夜中によく目が覚める人
✔︎ 朝早く目が覚めてしまう人
✔︎ 不眠に興味がある人
良い睡眠をとるための生活習慣
良い睡眠をとるためには不眠の原因となる生活習慣を改善することが非常に重要です。
下図の1日の流れを参考にして、生活習慣を見直すことが大事です。

不眠の問題を解決するために睡眠に関する正しい知識を身につけ実行することが大切です。
以下の注意点を理解し、実行するだけで不眠が解消される場合もあります。
睡眠に関連した生活習慣を見直してみましょう。
就寝・起床時間を一定にする
睡眠覚醒は体内時計で調整されていまるので、毎日一定のリズムで寝起きするのがベストです。
週末に夜ふかししたり、休日の寝坊したり、長時間の昼寝は体内時計を乱し不眠の原因になるので注意が必要です。
平日・週末にかかわらず同じ時刻に起床・就床する習慣を身につけることが大事です。
睡眠時間にこだわらない
睡眠時間は人それぞれで、年齢によっても変わります。そのため、今の自分にとって日中調子よく過ごせるための睡眠時間がどの程度かを知ることが大切です。
極端に睡眠を削ったり、逆に体と脳がそこまで睡眠を欲求していないのに、健康のために必要と思い込んで必要以上に長くしようと欲張ることは睡眠のトラブルのもとになります。
また、「◯◯時間眠りたい!」と目標を立てないでください。目標を立ててしまうと、予定通り眠らないといけないと気持ちが焦ってしまいます。予定を立てた就寝時刻が過ぎてしまうと、目標睡眠時間が達成できないので、ますます焦って寝れなくなってしまいます。
床に入っても「なかなか寝つけない」ときには、床から一度出て、リラックスして眠くなってから床に入り直すといいでしょう。寝床にいる時間が長すぎると熟眠感が減ります。
日中に眠気があるときは午後3時前までに30分以内の昼寝をとると効果的です。それ以上眠ると夜眠れなくなるので要注意です。
太陽の光を浴びる
太陽光など強い光には体内時計を調整する働きがあります。光を浴びてから14時間目以降に眠気が生じてきます。
早朝に光を浴びると夜寝つく時間が早くなり、朝も早く起きられるようになります。目から入った光を脳が感じることで体内時計が1日を刻み始め、夜になると眠くなるよう準備を整えます。
すなわち「早寝早起き」ではなく「早起きすることが早寝につながる」のです。逆に夜に強い照明を浴びすぎると体内時計が遅れて早起きが辛くなります。
不眠を訴える患者さんの多くは、日中引きこもりがちなんです。
家から出れなくても、朝はカーテンを開けてベランダにでて朝日を眺めるのをお勧めしています。無料で効果的な方法ですからね。
適度の運動をする
運動習慣のある人は不眠になりにくいことが知られています。軽い適度な運動を定期的に行うことも熟睡を促します。
ほどよい肉体的疲労は心地よい眠りを生み出してくれます。運動は午前よりも午後に軽く汗ばむ程度の運動をするのがよいようです。
短期間の集中的な運動よりも、負担にならない程度の有酸素運動を長時間継続することが効果的です。
自分流のストレス解消法を
ストレスを完全に取り除くのは不可能ですが、ストレスを軽減する方法は自分なりの解消法を身につけておくことも大事ですね。
当たり前ですがストレスは眠りにとって大敵です。
音楽・読書・スポーツ・旅行など、自分に合った趣味をみつけて上手に気分転換をはかり、ストレスをためないようにしましょう。
不眠の診療をしていると、ストレス解消法が見つけられない、趣味がないという人に不眠が多い印象です。
寝る前に自分にあったリラックスタイムを
睡眠前に副交感神経を活発にさせることが良眠のコツです。
ぬるめのお風呂にゆっくり入り、好きな音楽や読書などでリラックスする時間をとって心身の緊張をほぐします。半身浴は心臓への負担も少なく、副交感神経を優位にさせ、睡眠の質を向上させてくれることが分かっています。
様々なリラックス方法が提唱されていますが、同じ方法でも人や状況によってかえって緊張を促す場合もあり、自分にあった方法を見つけるのがいいですね。
特にTwitterなどのSNSを見ると、イラついたり、不安に駆られるようなコメントが少なくないので、副交感神経より交感神経が活発になってしまいます。
スマホの光も眠気を妨げてしまいます。
寝酒は厳禁
お酒は睡眠にとって百害あって一利なしです。特に深酒は禁物です。
寝酒をすると寝付きが良くなるように思えますが、効果は短時間しか続きません。飲酒後は深い睡眠が減り、早朝覚醒が増えてきます。
お酒は楽しむものであり、不眠対処に使ってはなりません。
患者さんの中には、そうしないと寝れないと訴える人がいますが、のちのち破綻してしまうので、そうなってしまったら、必ず病院を受診してください。
快適な寝室づくりを
眠りやすい環境づくりも重要なポイントです。
ベッド・布団・枕・照明などは自分に合ったものを選びましょう。
多少お値段が高いベッドや枕でも睡眠にはお金をかけて良いと思います。
温度や湿度にも注意が必要です。睡眠のための適温は20℃前後で、湿度は40%-70%くらいに保つのが良いといわれています。
交代勤務者のための睡眠の取り方
看護師さん、介護士さん、警備員さん、24時間営業の店員さん、夜間も勤務しなくてはいけない工事関係者の方々など、不眠を訴える患者さんが少なからずいます。
週に1〜2回は夜勤、そのほかは日勤というリズムだと、寝ても熟睡感が得られないだけでなく、精神的な不調も感じやすいのは間違い無いです。
すこしでもストレスをよくするために生活習慣、リズム、ストレス解消法を見つけていきたいです。
交代勤務の人は、主治医の先生に必ずお薬をいつ内服したらいいか確認しましょう。
夜勤の過ごし方
休憩時間の取れる時間にもよりますが、できれば60分間は仮眠をとるとよいとされます。理想的には2時間ですが、なかなか難しいでしょう。
夜勤中の仮眠1時間は、夜勤前の仮眠3時間に匹敵する効果があると報告されています、
夜勤後の疲労感も軽減しやすいと言われています。
仮眠をとりやすい環境にも注意が必要です。
できれば、仮眠専用の個室がベストです。少なくとも仮眠専用のスペースがあり横になることができるベッドは用意しておきたいです。
ラーメンや唐揚げなど高カロリーの食品は食べないことも大事です。健康上、よくないです。
夜勤明けの睡眠の取り方
まとめ
良い睡眠をとるための生活習慣
✅ 就寝・起床時間を一定にする
✅ 睡眠時間にこだわらない
✅ 太陽の光を浴びる
✅ 適度の運動をする
✅ 自分流のストレス解消法を
✅ 寝る前に自分にあったリラックスタイムを
✅ 寝酒は厳禁
✅ 快適な寝室づくりを
不眠の問題を解決するために睡眠に関する正しい知識を身につけ実行することが大切です。
上記のことに注意し、実行するだけでお薬に頼らず不眠が解消される場合もあります。
不眠を訴える患者さんには、まずお薬ありきではなく、一緒に生活習慣を見直すことから始めます。
生活習慣を改善するだけで、「よく眠れるようになりました」と改善することも少なくはありません。
ただ、上記にあげた生活習慣を改善するだけでは、不眠が改善するとは限りません。
その場合は、医師に相談して睡眠薬を処方してもらいましょう。
次の記事では、不眠症のお薬について解説します。








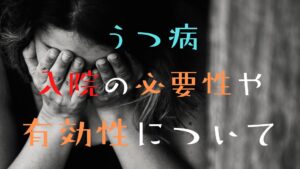
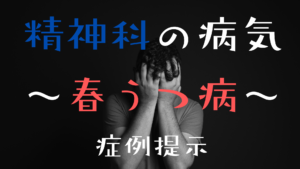

コメント